これまでの家選びの経過はこちら
住宅展示場→舞い上がる→見積もりともろもろの維持費にビビる→中古物件探してみる→変な不動産屋に当たり、よい物件を逃す→中古物件に疑問を持つ(今回)
その後も中古物件を探すも・・・
前回、よい平屋物件があったものの、変な不動産屋のおかげで取り逃してしましました。その後も、中古物件は色々と見に行ったのですが、結局のところ前回逃した物件以上のものはなく悩む日々が続きます。

あの不動産屋のせいで!!!
範囲等も広げ、いろいろと探しましたが、築年数が30年程度のものが多く、ある問題にぶち当たってしまうのです。
リフォーム代まで入れると2,000万円台に到達してしまう
前回逃した物件はリフォーム代まで入れても1,000万円台で済んだのですが、その後見た物件は何かしら直すところが多く、なんだかんだリフォーム代まで入れると2,000万円に到達するケースがほとんど。
リフォームと言っても、水回りやクロス、床部分のリフォームで断熱性能向上等のリフォームはしないものでその程度かかります。
2,000万円台と聞けば、本州の都会にお住いの方はめちゃくちゃ安いじゃん!となるかもしれませんが、北海道の地方部であれば基本的に3,000万あれば結構いい家が土地代入れて新築で建ちます。そのため、どうしても躊躇してしまっていました・・・・。
地方の中古住宅にお金をかけてリフォームする意味はあるのか?
新築に比べ断熱性能が劣るため、日々の光熱費がかさむ可能性が・・・
断熱性能向上リフォームもお金をかければ可能なのですが、そこまで手を入れようとするとリノベーションの域に到達してしまい、リノベーション費用だけで1,500万~2,000万程度かかってきてしまいます。
今回私たちが考えた、通常の水回りや壁・床のみのリフォームの場合、500万~600万程度で済むことが多いのですが、この場合は断熱性能は中古物件がもともと持っている性能に依存することになります。
そして、いろいろと拝見した物件で多かったのですが、築15年~25年程度の物件で非常にオール電化住宅が多かったのです。しかも、東日本大震災が起こる前の原発(泊原発)がたくさん稼働していた頃の電気料金メニュー(深夜電力の格安提供)をベースに考えられており、ヒートポンプ暖房ではなく蓄熱式の暖房器具が主流。消費電力は非常に多く、今の北海道電力の電気料金メニューだとかなり電気代がかなりかさむことは免れません。
拝見したとあるオール電化住宅では、冬季は月に6万程度電気代がかかるそうです・・・。このお宅は蓄熱暖房システムでヒートポンプシステムではなかったため、ヒートポンプへ変更するだけでもだいぶランニングコストは変わってくることは理解したものの、システム変更にもかなり費用が掛かるためやはり現実的ではありませんでした。

月に6万も光熱費にかかるって家賃レベルだね・・・
最近の新築物件では、一般的な住宅のレベルでも熱源に都市ガスや灯油・電気(ヒートポンプ)を採用すれば冬季の光熱費はおおよそ2万~2.5万程度となることが多く、前述の中古物件と比べるとその差は4万/月程度に達します。北海道の冬期間はおおよそ11月から3月までの5か月間。その期間内でも上下はありますが、単純に月4万の差と考えれば年間20万円ものロスが見込まれます。
以前の記事でもお伝えしている通り、北海道において冬季の暖房費の負担はかなりのものになり、熱源選択も非常に重要となりますが、中古住宅では自分の希望の熱源選択が必ずしもできるわけではありません。
結局、築20~30年レベルの物件では断熱性能は当然現代の住宅と比べ大幅に劣りますし、その上、拝見させていただいた物件の多くがオール電化の蓄熱式暖房・・・。
この部分がネックになり、かなり安価な物件じゃないとメリットが見えてこないため、やはり話はなかなか前に進みませんでした。
売却時の残存価値が見込みにくい
中古住宅を探して気づいたのですが、リフォームしていようと、リノベーションしていようと築年数自体は変わりません。そして、中古住宅を探すときは築年数でフィルタリングをかけていろいろと見ていく訳で、今築30年の物件を買ってリフォームをかけて20年後に売却するとなった時、その物件は築50年となっています。
少子化が目に見え、人口減少が顕著な地方部で、築50年の物件に価値が付くのかと言えば、ほぼ土地代しか残らないことが容易に想像がつきます。下手をすれば解体費分差し引かれるかもしれません。

築50年って言われると・・・。
確かに厳しいかも・・・。
そう考えると、そういった物件に総額2,000万円もかける価値があるのか・・・。疑問がふつふつと湧いてきました。
新築に比べメンテナンス費用が掛かることが目に見えている
築年数が古めの中古物件の多くは不動産業者等によってリフォームや外壁塗装がすでにされているものが多く、パッと見あまり手がかかりそうにないものが多いですが、外壁(サイディングの張替)や屋根下の防水シートの交換、配管関係の取り換えなど、当たり前ですが、新築に比べればメンテナンス費用の発生は多く見込まれます。また、給湯器具等の交換の可能性も高くなります。
築年数が15年程度と浅ければその辺もあまり考えなくてもいいのかもしれませんが、そのあたりの年数だと物件自体がそもそも高額で、水回りリフォームのみであっても新築とあまり価格差が無くなってきます。
このようなことを考えると、やはり築20年程度の程度の良い中古物件を1,000万前後で購入できなければ新築に比べうまみが少ないと考えられます。
新築の時に得られる各種補助金が中古+水回りリフォームの場合ほとんど得られない
中古物件の場合、現時点で得られる補助金は、既存住宅売買瑕疵保険に加入した物件がすまい給付金の対象になるのみです。住宅ローン減税はもちろんありますが、あくまでも減税。
次世代住宅ポイント制度は、若者・子育て世代の既存住宅購入後リフォーム項目の10万ポイントは確実に得られますが、そこからの上乗せはあまり大きな額が見込めません。
断熱性能を大幅に向上させるようなリノベーションになってくると、長期優良住宅化リフォーム補助金が100万~300万、省エネ改修補助金が最大120万とかなりの補助金が見込まれますが、そこまでのリノベーションを行うと1,500万~2,000万以上かかるため、現実的ではありません。(おそらく政府もリノベーションに多額の費用が掛かることを見越してこのような高額な補助金としているのでしょう)
一方、新築の場合は、すまい給付金(MAX50万)のほか、次世代住宅エコポイントに加え、地域型住宅グリーン化事業(長期優良住宅等)の場合で50万~140万、または、ZEH関係の補助金が70万~125万(太陽光発電必須)と、あまりハードルが高くないもので高額な補助金がもらえる可能性が高いのです。
また、長期優良住宅やZEHレベルの住宅性能であれば、フラット35の利率軽減制度、フラット35Sを適用することも可能となり、支払総額を抑えることも可能です。
結局、中古物件+リフォームにあまり魅力を感じることが出来なかった
これまで触れてきたことを考えてきた結果、中古物件+リフォームとして新築よりお得感を出すには、築20年程度で1,000万円程度の程度のよい物件を探す必要があることが分かってきました。
前回、変な不動産屋のせいで逃した物件は、まさにその条件に適合する物件でした。しかし、その後結局その物件に匹敵するような物件は出てきませんでした。
そして、ヨメが中古物件を探していくうちに、建売(新築)の格安物件を見つけるようになりました。

この物件、新築なのに安くない?
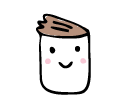
ん?1,980万?土地付き新築なのにかなり安いねぇ・・・
私が目にしたのは、80坪の土地+新築3LDKの物件。希望の市ではないですし、地区もあまり人気のあるエリアではありませんが、この価格で家が建てられるのか・・・と驚きました。
そこの物件の土地価格の相場はおおよそ3~4万/坪でしたので、差し引きして、家自体は約1,600万で建築されていることになります。もちろん、立派な建材等を使っているわけではなく、キッチンやトイレ・お風呂は最低グレードレベルでしたし、コスト増につながるトリプルサッシも使われていませんでした。ただ、逆に良い設備を入れていたらどこでコストカットしているのやら・・・と不安になったのでいい意味で納得。
当たり前ですが、20年~30年前の中古住宅と比べれば建築基準等も変わっていますので、いくら安い家だと言え、断熱性能等の違いは歴然。中古住宅を買ってリフォーム等を行い、総額2,000万弱程度で暮らすか、ややコンパクトだし、窓が小さかったり設備グレードが低いながらも、お安い新築住宅で暮らすのか。
ヨメともいろいろと話はしましたが、暖房コストや再販時の残存価値を考えた結果・・・、後者がやはり有利なのではないかとの考えに至りました。
この低価格住宅との出会いが私たちの家選びをまた変えていくことになります。
この続きはまた次回!


























